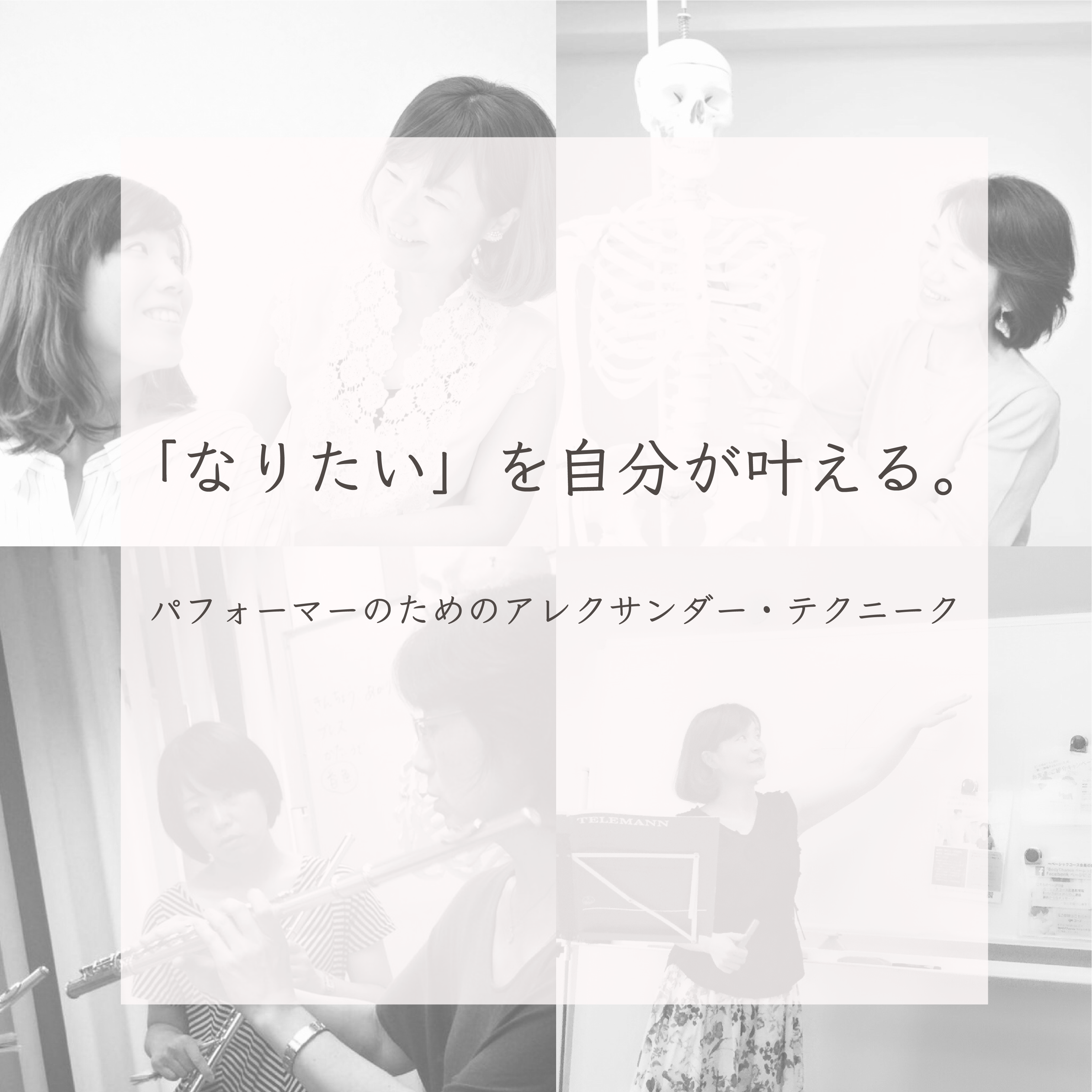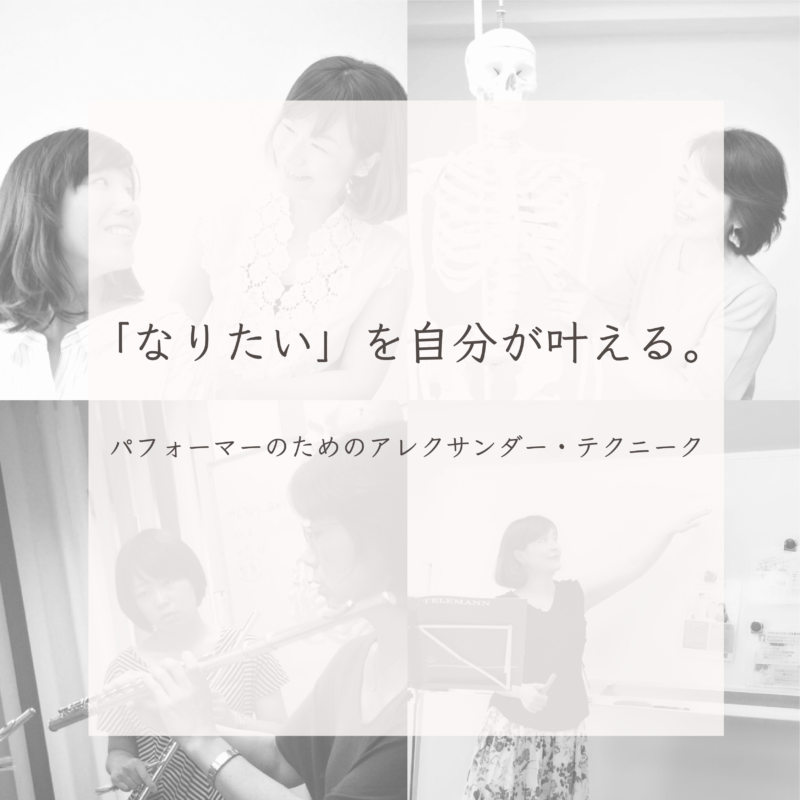セルフ・クエスト・ラボでは資格を発行しません。
セルフ・クエスト・ラボのティーチャーコースを修了したことを認定されたら、ATIのアセスメント(ATIスポンサー教師による資格認定試験)受験の推薦状を発行いたします。
3人のスポンサー教師の資格認定試験(アセスメント)に合格すると、ATI認定資格が発行されます。
スポンサー教師との交渉は基本的にはご自身で行っていただきます。海外教師の場合は、英文の書類作成などに関して可能な限りサポートいたします。
ATI認定資格試験に関することはセルフクエストラボでも随時情報を集めていますので、お尋ねください。ラボ・クラス設立に関してはATIの幹部でもあるキャシー・マデン先生にもアドバイスをいただいています。
スポンサーシッププロセスを通じてATIの教育メンバーになるための大まかな手順
1. 各種申請書類、レポートの準備
↓
2. スポンサーシップの教師にアセスメントを申し込む(→通訳の依頼と生徒さん及び会場の手配)
↓
3. アセスメントを受ける(2.〜3.を3回繰り返す)
↓
4. ATI本部へ申請をする
↓
5. 会費を支払う
↓
6. ATI本部より認定証の発行
1) ATIホームページについて
以下、ATIホームページの各ページについてリンクを添えながら解説します。
*ATIホームページ https://www.alexandertechniqueinternational.org
すべての情報がこのホームページ内に書かれています。言語選択をすれば日本語でも読めるので、なるべくすべての情報に目を通してください。
*ATI教師になる https://www.alexandertechniqueinternational.org/become-an-ati-teacher
こちらのページ内の「認証プロセス」が認定試験の内容です。
*認証プロセス https://www.alexandertechniqueinternational.org/certification-process
ATI教師としての能力を認定する基準が書かれています。教師として求められる資質や人間性、知識、レッスンスキルが示されています。これはよく読んでおいてください。
このページに加え、以下「ATI認証手順」 「知識体系(知識のボディ)」「ATIスポンサー」の3つのページに分かれてさらに情報があります。
*ATI認証手順 https://www.alexandertechniqueinternational.org/certification-process
(ページ内の「スポンサーシップを介して」とは、3人のATIスポンサー教師(認定審査のできる教師)の推薦を得るとATI教師認定される、ということです。)「以下の知識を研究および実証するためのガイドライン」は2022年に新たに加わった項目です。
*知識体系(日本語で「知識のボディ」と表記されているページ)
https://www.alexandertechniqueinternational.org/body-of-knowledge
冒頭に書かれている「知識のデモンストレーション」が新しく加わった認証プロセス。
「教育スキルのデモンストレーション」は、これまで同様のティーチング(レッスン)の実技のことです。
*ATIスポンサー https://www.alexandertechniqueinternational.org/ati-sponsors
アセスメントを受けられるスポンサー教師のリストです。
これまでSQL教師と修了生が受験したのは以下の方々です。(敬称略)
キャシー・マデン、トミー・トンプソン、デビ(デボラ)・アダムス、石坪佐季子
*認識プロセス https://www.alexandertechniqueinternational.org/recognition-process
資格申請について書かれています。
3人のATIスポンサーより推薦状のサインを頂いたのちに、ATI本部へ資格申請をします。
必要書類をメール添付でオンライン申請できます。申請が受理されて年会費をクレジットカードで支払い、入金完了後に資格取得完了です。
手続きが終わり次第、認定証が郵送されます。1〜2ヶ月かかることが多いです。
2)「知識体系(知識のボディ)」について
アレクサンダー・テクニークに関する知識を適切に備えているかどうかを確認するレポート提出が認定プロセスに加わり、2022年3月現在試行期間に入っています。
設問の内容は、これまでアセスメント後の口頭試問内で聞かれていたものに似ていますが、今回の改定で、より確実に知識の有無を尋ねる内容となっています。
現時点でこのプロセスを使う教師と使わないスポンサーが混在しています。また、完全なレポートを求めず、アセスメントの最後に口頭で聞く方法をとる教師もいます。
新方式では、アセスメントが決まったら、実施日より前に指定された別の教師( 知識に関するレポートをチェックする担当教師=Reviewer)に提出するようですが、今の所はアセスを受ける教師の指示に従ってください。念のため早めにレポートを準備しておくと安心だと思います。
この新しい措置は、ATI教師メンバーの最低限の知識レベルの確保のためと、アセスメントを担当するスポンサー教師の負担を減らすためです。知識体系の事前チェックによりスポンサー教師が試験実施の際にティーチングスキルの評価と受験者への建設的なアドバイスをすることに専念できるようにするためです。
またReviewerは教師認定候補者の回答を評価することはしません。Reviewの目的は受験者の知識体系の正確さをチェックし、仮に不足している場合はアセスメントの前に話し合ってレポートを完成させるサポートをすることだそうです。
実技試験前に文書で提出する項目は「アレクサンダーの著書」「解剖学」「倫理規定」の3つです。
*なお、アセスメント(assessment)ではなく、エヴァリュエーション(evaluation)という言い方をするスポンサーもいます。
①アレクサンダーの著書(F.M.アレクサンダーさんの大まかな履歴を含む)
「知識体系(知識のボディ)」のページに例文が載っています。
また、別のページ(見つけにくいですが)には以下の通りサンプルの質問が明記されています。
https://www.alexandertechniqueinternational.org/assets/docs/Prompt%20for%20the%20ATI%20Demonstration%20of%20Knowledge%20of%20Alexander.pdf
これに、ATIからトレーニングスクール宛てに送られてきたメール内の該当する内容を加えてまとめた「課題サンプル」の和訳がこちらです。↓
アレクサンダーの著作に関する知識のATIデモンストレーション課題サンプル
・・・以下、嶋村より。
以上のことから、私たちからのラボ・クラス修了生へのアドバイスとして、レポートには次のような内容が含まれ、”あなたの言葉で” 書かれているのが望ましいと思います。
・フレデリック・マサイアス・アレクサンダー(Frederick Matthias Alexander 1869-1955)オーストラリアのタスマニア生まれ、1955年イギリスのロンドン没。
・朗唱劇の役者だった
・声のトラブルをきっかけとした発見
・自己観察と自己の習慣の認識から様々な考察に至る
・初期は、呼吸の改善(再教育)を得意としていた
・原理(アイデア、概念)を自分(あなた)の言葉で説明する
・著書は4冊。(題名の和訳は一例です)
「Man’s Supreme Inheritance(人類が受け継いた最高のもの、人間の最高の継承)」
「Constructive Conscious Control of the Individual(個人の建設的意識的コントロール、管理)」
「The Use of the Self(自己の使い方)」
「The Universal Constant in Living(生きる上で普遍的なこと、生きる中での普遍定数)」
・FMがこのワークの原理を発見した経緯が書かれているのは「The Use of the Self」の第1章「テクニークの進化(Evolution of the Technique)」初めての人にはこちらを勧めるのが妥当と思われます。
・FMアレクサンダーの弟ARアレクサンダー(アルバート・レディンAlbert Redden 1874-1947) とともにワークを発展させた。ARはFMをサポートしてスクールを手伝い、さらに独自の教え方も開発し、アメリカにワークを広めたと言われている。
ATIホームページ内「知識体系(知識のボディ)」のページの最後の質問、「F. マティアス アレクサンダー テクニークを構成する明確な理論と知識体系を参照し、人間の使用と機能を改善する他の手段と区別してください。」に関しては、こちらに資料があります。
https://www.alexandertechniqueinternational.org/assets/docs/Distinct-theory-and-body-of-knowledge2.pdf
和訳はこちらです。↓
「3つの報告書」(長文です)
※ アレクサンダーさんの経歴やアレクサンダーテクニークに関するたくさんの資料をAT教師のヤスヒロ(石田康裕)さんが公開しています。4冊の著書の要約や弟のAR・アレクサンダーについての記事もあります。参考にしてください。
FMアレクサンダーについて http://yasuhiro-alex.jp/f-m-alexander/
ARアレクサンダーについて http://yasuhiro-alex.jp/2017/10/04/ar1/
FMの著書とその他の文献 http://yasuhiro-alex.jp/fmwriting/
※ FMの著書4冊の要約本の翻訳版も出版されています。
ロン・ブラウン著(八木道代 日本語版監修)「アレクサンダー・テクニーク」
②解剖学的知識
こちらもホームページに質問サンプルがあります。
https://www.alexandertechniqueinternational.org/assets/docs/Anatomical%20Questions.pdf
和訳はこちらです。↓
ATI 解剖学的知識デモンストレーションの課題サンプル
③倫理規定について
ATIホームページの倫理規定ページはこちらです。日本語で読めます。
https://www.alexandertechniqueinternational.org/code-of-ethics
これまでのアセスメントでは、倫理規定から1つ項目を選び、それを選んだ理由とどう考えているかの文書を提出、もしくは口頭で伝えていました。
倫理規定に関する新しい課題質問には、「シナリオ(架空のシーン、場面想定)」より指定された数の項目を選んでコメントするようにとなっていますが、「シナリオ」はホームページ上では公開されていません。ATIメンバーページ内で英文では見ることができます。
現在は、知識のデモンストレーションプロセスを使用するスポンサー教師から直接指示があるようです。
※倫理規定のシナリオの和訳はこちらです。↓
「倫理シナリオ」
文化の違いもあり内容の中には日本人の解釈が難しいものもありますが、人権尊重や金銭契約などについての常識的判断を再認識する機会になると思います。
まだ試用期間なので様々なケースが予想されます。
特に、デビ・アダムズ先生はATIの委員でもあり、早速運用を始めているようです。
いずれにしても、変化に関してはたいへん親切にガイドし、個々への配慮のある組織ですので安心してください。今後はそれぞれスポンサー教師から知識のデモンストレーションについての指示を受けて対応してください。
・・・最後に、
ATIが「知識体系のデモンストレーション」を導入するにあたり、かなりの年月を費やして賛否両論を出し合い、相応しいと思われる方式を作成したと聞いています。
その理由は、日本では想像できないほどの多様性を含む世界の文化においては、実に様々なトレーニングスクールがあるそうで、ATIはその多様性を許容しながらも、教師認定には最低限のクオリティコントロールが必要と判断したからです。
Self Quest Labを主宰する2人の教師たちは、ラボ・クラス設立の際に自分たち自身がATIの認定を受ける過程で必要性を感じた学習要素をカリキュラムに加えることを意図して学びのプロセスをデザインしました。レポート課題や口述試験もその一部です。
ですから、ラボ・クラスでの学びはATIの教師認定に充分対応できるものと考えています。
資格取得費用についてですが、スポンサーに支払う受験費用は各回ごとに確認して支払います。基本的には1回につき100$(米ドル)共通と聞いていますが、教師により違うこともあります。
アセスメントに通訳が必要な場合は通訳料などをご自身でご確認の上依頼してください。
SQLからは松代尚子さんをおすすめいたします。
資格申請後にATI教師メンバーの年会費を支払います。(ホームページでご確認ください)
ラボ・クラスでの教師養成トレーニングを修了後、ATI資格をとるかどうかは自由です。
ATI教師資格の取得やATIメンバーとして所属することは各自の意思により決めてください。
今後も情報収集を続け、かつ歴史あるATの真髄を捉える真摯な学びを提供できるように努めて参ります。何か変化があれば、その都度対応をしていきたいと思いますので、皆さんもわからないことがあればいつでも相談してください。
*申請時の提出書類などは追加変更の可能性があるので、随時確認して対応してください。
*ご相談はお気軽に嶋村、渡邊または事務局までどうぞ。officeselfquest@gmail.com